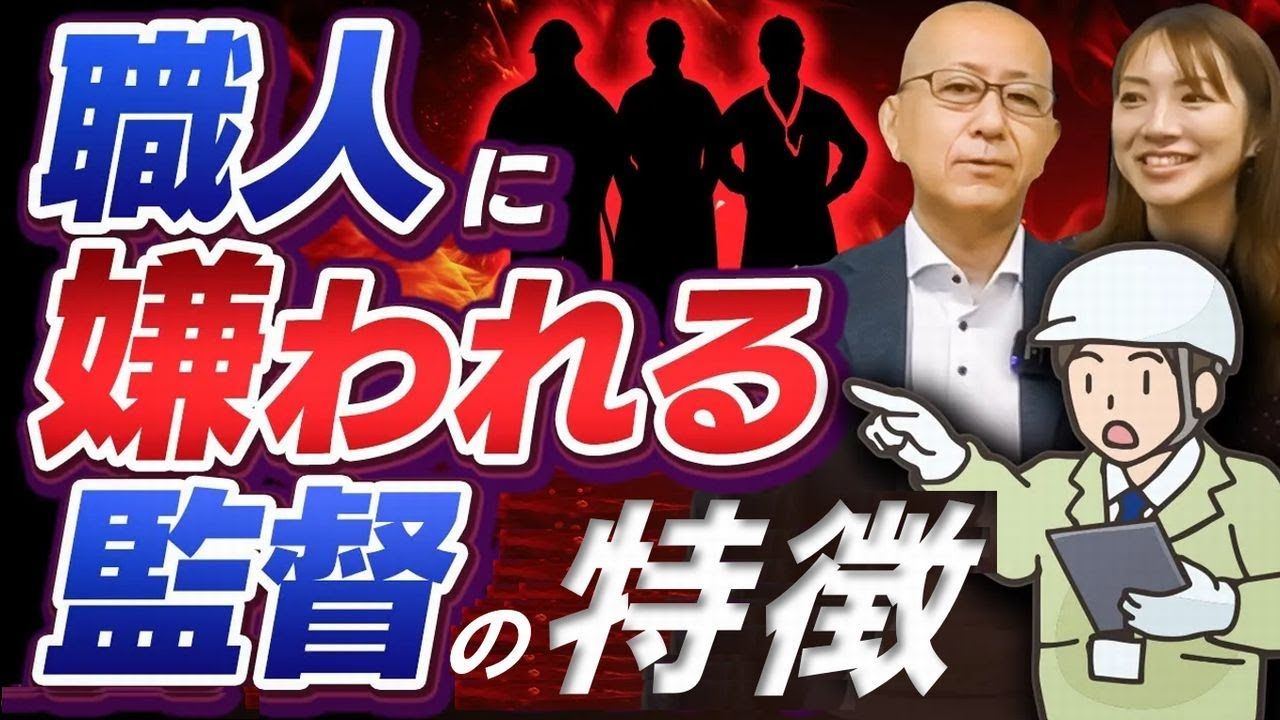受注者から発注者へのクレーム!国土交通省に寄せられたリアルな意見を紹介
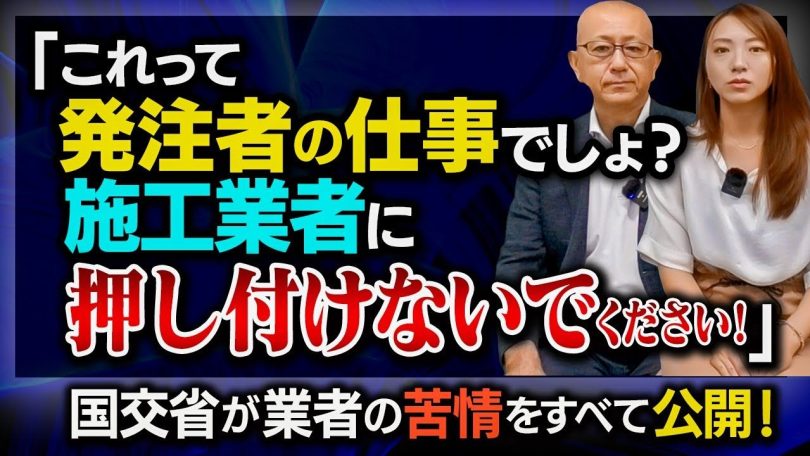
「あの発注者、仕事を押し付けてきて困る!」
「発注者の好きなタイミングで電話連絡が来て迷惑!」
受注した仕事を進めていく中で、発注者に対してクレーム・苦情が出ることもありますよね。
オブラートに包んで伝えたとき理解されなければストレスですし、今後の関係性を考えると強い言葉で伝えるわけにもいきません。
国土交通省の九州地方整備局では、クレーム・苦情・意見を受け付ける、意見の窓口を開設しました。
本記事ではここに寄せられた意見として下記の3つを紹介します。
- 職員の対応
- 監督補助員について
- 作業時間外の連絡について
これらの意見を知ると、あなたが発注者の立場になったときの注意点や振る舞い方が分かります。
昔からの名残で間違った対応をしてしまう場合もあるので、まずは1つずつ内容を確認しましょう。
国土交通省九州地方整備局の取り組み「意見の窓口」

国土交通省の九州地方整備局では、いきいき現場づくりという取り組みを実施しています。
その取り組みの中で「意見の窓口」を開設。
九州地方整備局の発注した工事・業務を受注した会社の人に意見を投稿してもらっています。
—–
九州地方整備局では、公共工事の円滑な執行を図り、利用者(住民)への安全・良質な品質の社会資本を早期に提供するため、ワンデーレスポンス、工事監理連絡会、設計変更協議会、工事書類の簡素化などの施策により、発注者及び受注者が各々の責務を果たしながらコミュニケーションを強化する『いきいき現場づくり』に取り組んでいるところです。
「意見の窓口」とは、『いきいき現場づくり』の施策等を実践している受注企業の現場に携わる技術者の皆様からご質問やご意見を受け付ける窓口です。さらに、平成27年11月より業務版の意見の窓口を開設いたしました。皆様からのご質問やご意見については、回答・コメントをホームページで公開していきます。
—–
意見の窓口に寄せられた、受注者から発注者へのクレーム・苦情を紹介します。
受注者から発注者へのクレーム①:職員の対応について
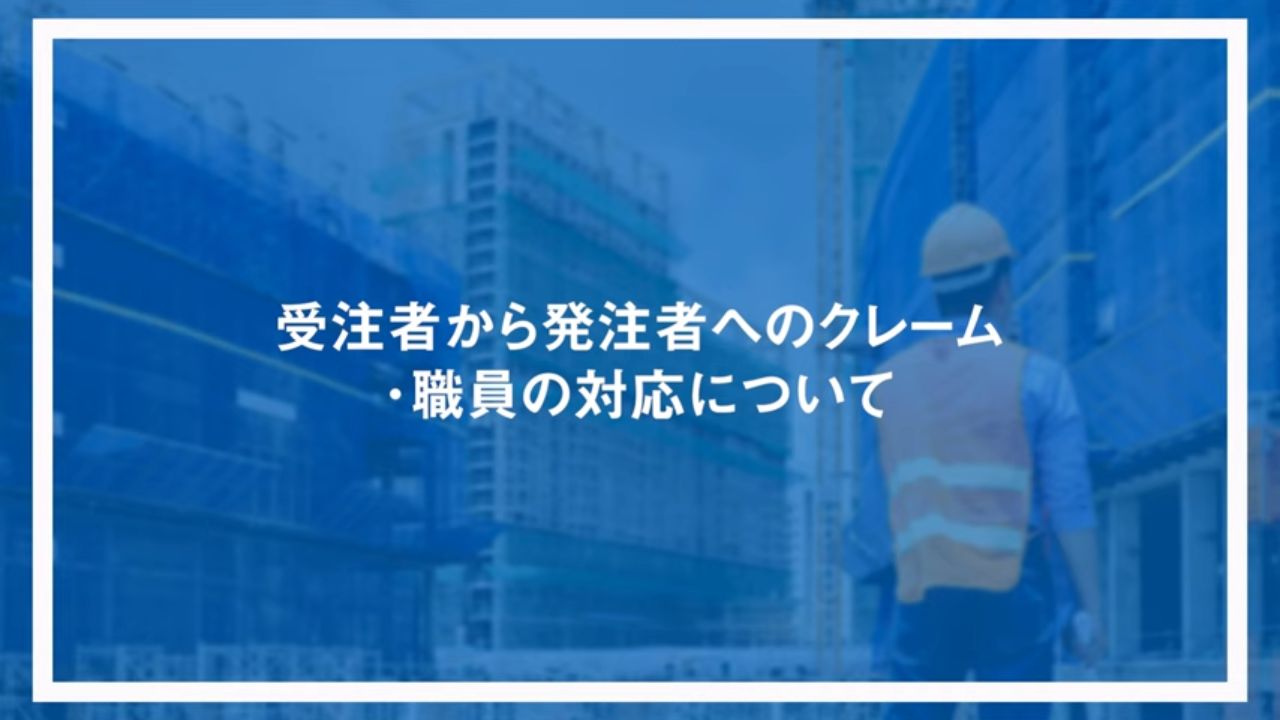
意見の窓口へ届いたクレームの1つ目が「職員の対応について」です。
国土交通省の職員の対応について、クレームがありました。
—–
威圧的な態度・不機嫌な態度は当たり前。自分は良くて人に厳しいタイプ。行くところ行くところで問題ばかり。自分が気に入らなければすぐ態度に出す。今まで他業者が善意で行ってきたことも押し付け、断れば決まって不機嫌。業者の気持ちは無視。威圧的な態度・不機嫌な態度をとられるとコミュニケーションをとろうとも思わない。●年間もそんな態度でそろそろみんな限界にきてますよ。
—–
腹に据えかねている受注者の想いが伝わってきます。
善意で他の業者がやった業務を押し付けられ、「あの会社はやってくれた!何でやってくれないんだ!」と嫌な態度を取られたのでしょう。
受注者の立場や状況を考えない威圧的な態度は、意思疎通・コミュニケーションもうまくいかない原因になります。
受注者から発注者へのクレーム②:監督補助員について
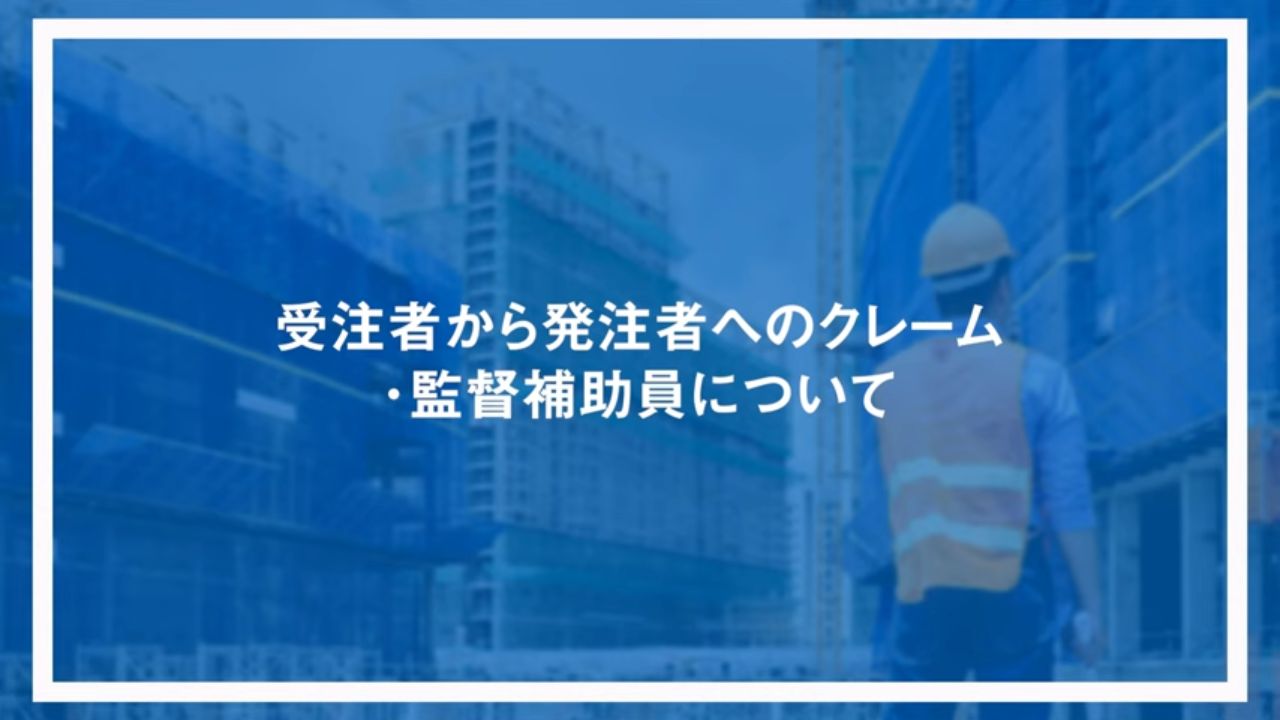
意見の窓口に届いた「監督補助員について」のクレームもありました。
発注者支援業務と呼ばれる、役所の職員の補助を行う人たちのことです。
株式会社ライズで運営している、発注者支援業務チャンネルで業務内容を詳しく学べます。
発注者支援業務チャンネル @株式会社ライズ
クレームは事務所名や氏名など、実名で書かれたようです。
ホームページ上は名前を伏せられていますが、受注者側も覚悟の上名指しの苦情を入れています。
—–
変更数量計算書及び変更契約図面の作成は、貴方の仕事ではないですか?
請負業者の仕事ですか?
変更資料を○○○事務所へ持込時に、なぜ私たち請負業者が忙しい中に時間を、割いて同席をしないといけませんか?
貴方が作成していないため説明できないからじゃないですか?
今後も変更数量計算書、変更契約図面は請負業者に作成させますか?
—–
変更数量計算書・変更契約図面のような設計変更に関係する図書作成は、基本的に役所側の仕事です。
受注者の仕事ではないのに押し付けられた、というクレームです。
さらに変更時の説明にも同席させられたこともクレームとして挙がっています。
受注者に作らせた資料なので、作った本人しか説明ができないからです。
最近はどちらが資料を作成するか、線引きを明確にしたマニュアルもあります。
国土交通省も厳しく言っているのですが、昔からの名残で受注業者へ作成を任せるケースも多いのが現状です。
クレームの通り、「工事の設計変更に必要な図書は監督補助員が作成し提出する」という決まりを認めています。
工事図書等作成支援の手引きにも、作業内容を記載していると回答がありました。
発注者が受注者へ仕事を押し付けるのは、受注者にとっては負担となります。
国土交通省も手引き・マニュアルを作成して対処しています。
受注者から発注者へのクレーム③:作業時間外の連絡について
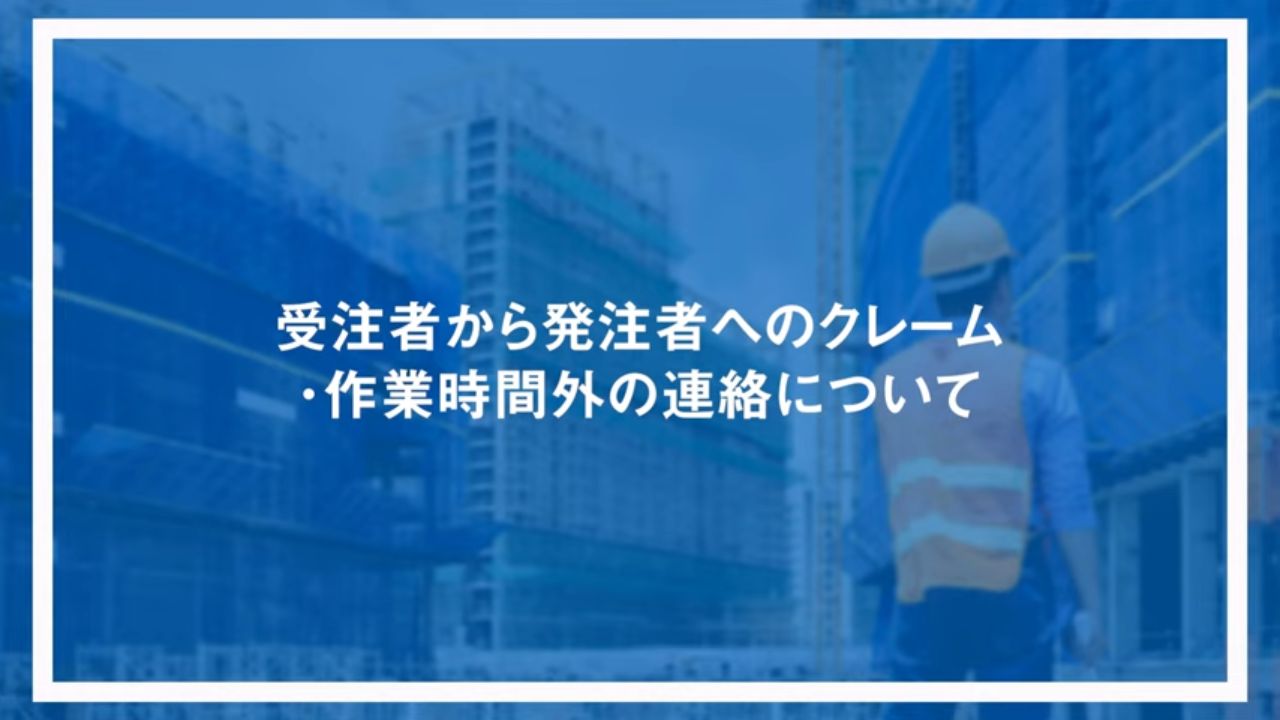
意見の窓口には「作業時間外の連絡について」のクレームも届きました。
—–
当工事は昼勤と夜間の作業がある工事です。
国交省の職員の方、監督補助員の方に昼間作業担当と夜間作業担当を伝えているにも関わらず、寝ている時に当たり前のように電話が掛かってきます。
緊急の電話であればこのような所に意見しませんが、メールで済むような事や緊急を要さない事が大半です。
4月からの残業規制もあり会社は色々と対策をしてくれていますが、発注者の配慮の欠如やそもそものモラルが低いため慢性的な寝不足になりノイローゼになりそうです。
—–
発注担当者に直接伝えることも考えたそうです。
しかし「対応が悪い」と工事評定点で仕返しをされたくないので、匿名で意見をしたという状況です。
働き方改革で様々な取り組みがなされている今、出勤時間外・作業時間外に電話連絡があることに疑問を感じます。
役所からは、下記の指導をしたと回答がありました。
- 昼間・夜間の担当を職場内で共有
- 緊急以外の連絡はメールで行う
電話連絡は、手っ取り早く報告・伝達ができる便利なツールです。
一方で相手の時間をうばっている点を再認識し、現場体制に配慮した連絡ツールを使っていくべきと言えます。
まとめ:受注者からのクレームを受け止めたいという国交省の本気が伝わった
発注者である国土交通省へ、受注者から意見・クレーム・苦情ができる「意見の窓口」。
役所がこの発案をし窓口を設置したことは、すごいことだと評価できます。
九州地方整備局の本気度がうかがえます。
国土交通省あてのクレームですが、発注者の立場になったとき気を付けるべきことが分かりますよね。
どんな仕事でも受注者/発注者・元請/下請など関係なく、良好な関係性を築くことは仕事をスムーズに行う上で大事です。
似た内容として、嫌われる現場監督の特徴4選!もまとめているので、あわせてご覧ください。
この記事の内容は、以下の動画で解説しています。あわせてご覧ください。