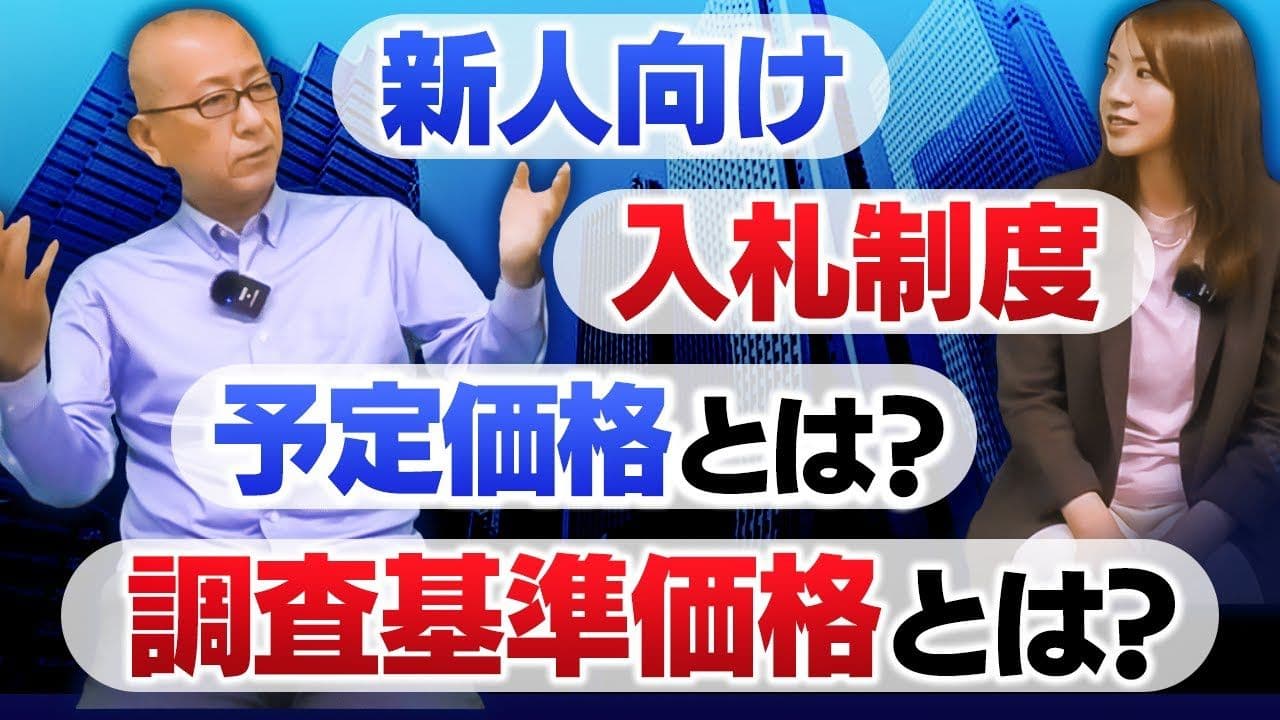談合から入札不成立の時代へ【土木工事のトレンド変化】案件は工事会社が選ぶ
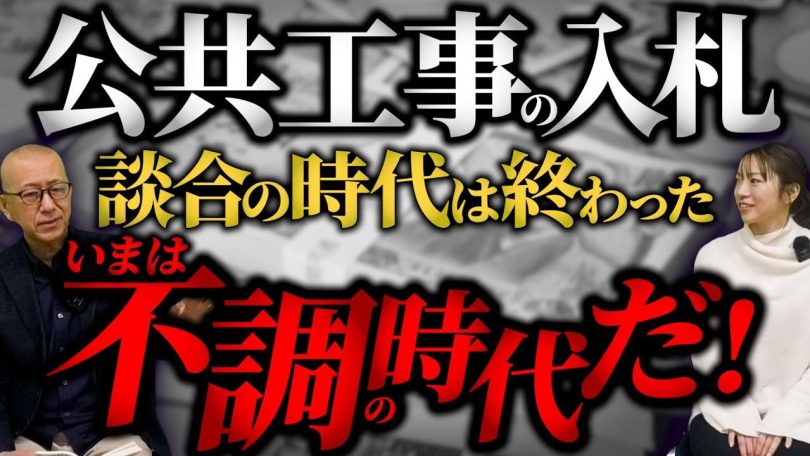
「土木工事って談合して入札するんだよね?」
「談合して利益を安定させるんでしょう?」
土木の公共工事について、このようなイメージをお持ちの人もいるでしょう。
そのイメージは、ひと昔前までは間違っていませんでした。
ただし今は違います。
トレンドは変わり、入札する案件は工事会社が選ぶ時代に変化しています。
本記事では、髙木健次さんの建設ビジネスより、談合の時代が終わった経緯と、入札不成立が増えている理由を説明します。
時代とともに土木工事にも変化が訪れています。
土木工事の今を知りたい人や、談合のイメージを持っている人は、記事を読んで新しいトレンドを知ってくださいね。
談合は終わり入札不成立の時代が来ている
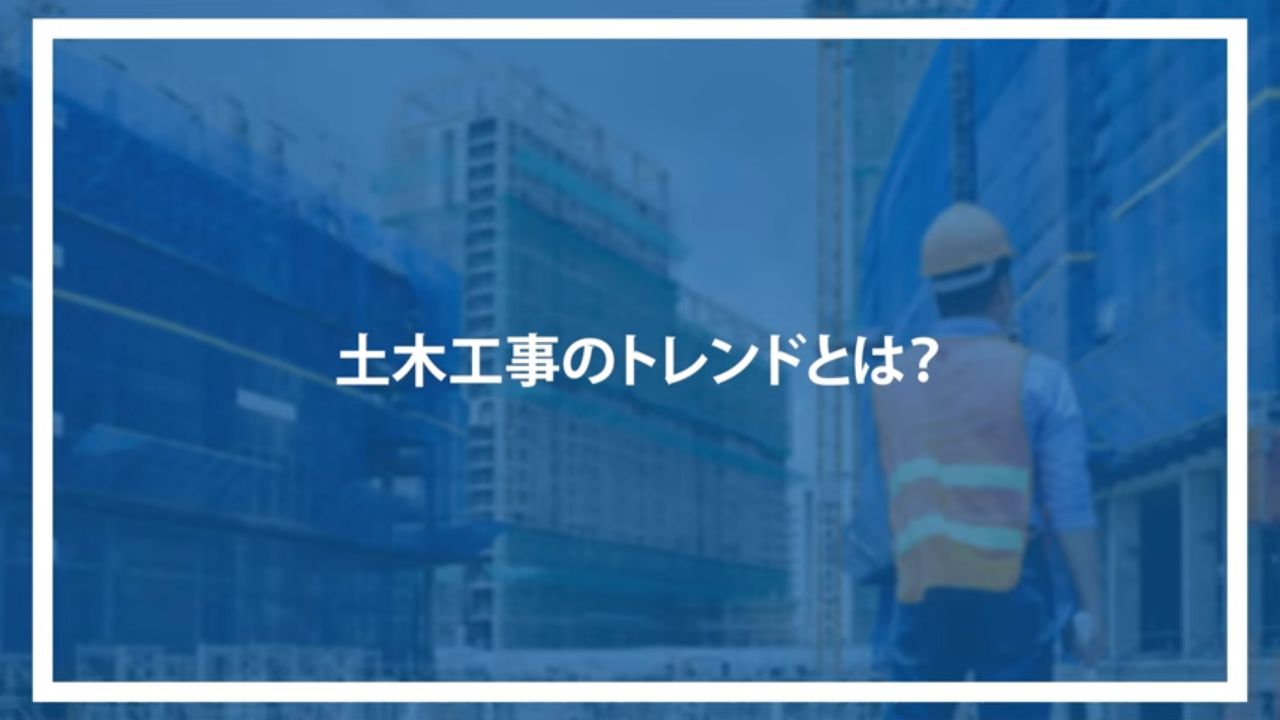
——————————
建設投資の統計を見ると土木工事の75%は国や自治体が発注する公共事業である
——————————
髙木さんが著書内で述べるように、土木工事の75%は公共工事です。
残りの25%は造成工事のような民間工事です。
- 整地
- 地盤改良
- 盛土
土地を活用するために、これらの作業で区画や形を造成する工事をいいます。
公共工事には談合のイメージを持っている人もいるでしょう。
入札価格を事前に調整する、談合。
この入札=談合のイメージ・トレンドは、すでに変わりつつあります。
汚職事件から脱談合宣言へ

1993年に起きた、ゼネコン汚職事件をご存知でしょうか。
大臣や市長、知事が次々と逮捕された、賄賂が絡む事件です。
参考:金丸前副総裁逮捕 ゼネコン汚職広がる
その十数年後である2006年、ゼネコンの業界団体は脱談合宣言をしました。
旧来のしきたりと決別する、と提言・発表。
その後は公共工事にどの会社も手を上げない、入札不成立も増えてきました。
「入札します。参加したい会社は手を挙げてください」と言っているのに、誰も挙げない状態です。
「誰もやらないの?」と聞いても、「シーン」とした状態を指します。
談合がなくなり入札不成立になる理由

入札不成立になる理由として、髙木さんは以下の指摘をしています。
——————————
資材価格・人件費の上昇に伴い自治体が決める価格で入札しても工事会社側が利益を確保できないため
——————————
公共工事では予定価格や最低制限価格など、ある程度の見積もりがされた状態です。
公共工事の入札制度についてはこちらの記事をお読みください。
これらの価格が提示されても見積額が合わなければ、工事会社は入札しません。
地方は人手不足もあり、職人の出張費にもコストがかかってきています。
人手不足のためコストが上昇しているにもかかわらず、自治体の見積もりが低いため入札不成立が増えています。
談合から入札不成立になった経緯
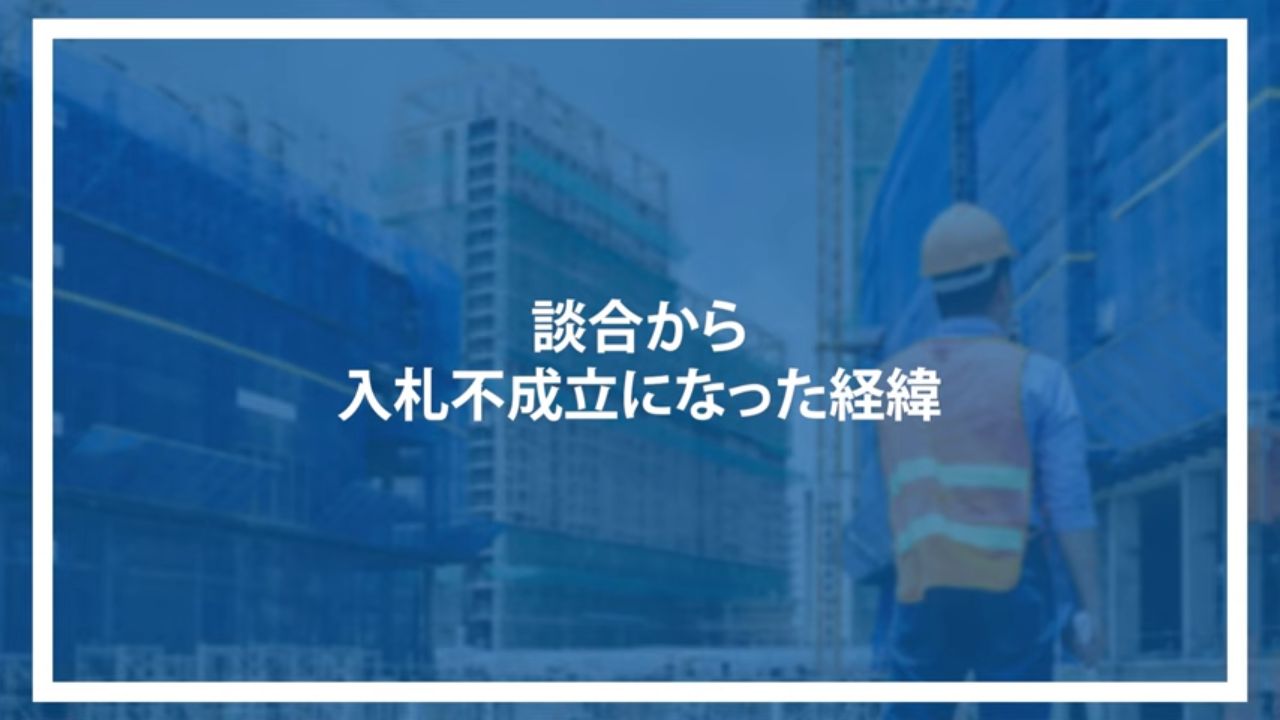
談合する理由として、過度な値下げ競争を避けて安定した利益を確保することをイメージする人が多いでしょう。
それだけではありません。
髙木さんは著書の中で、仕事を各社に配分するため、と理由づけています。
みんなで仕事を分け合うために、談合していました。
ただし今は状況が違います。
- 人手不足
- 高齢化
- 資材の高騰
このような状況下で、誰も工事しない現象つまり入札不成立が起きています。
工事会社が入札案件を選ぶ時代に変わってきた、といえます。
まとめ:土木工事の談合は終わり入札する案件を選ぶ時代に変わった
国全体としてこのような現象が起きているわけではありません。
「仕事が減ってきた」と話す、地方の工事会社もあります。
ただ入札するために談合するという時代は、終わりです。
人手不足や資材の高騰により、これからは工事会社が案件を選ぶ時代になっていくでしょう。
施工管理チャンネル by 株式会社ライズでは、土木を含む建設業界の情報を発信しています。
建設業界の裏話や今後を知りたい人は、ぜひチャンネル登録してくださいね。
この記事の内容は、以下の動画で解説しています。あわせてご覧ください。