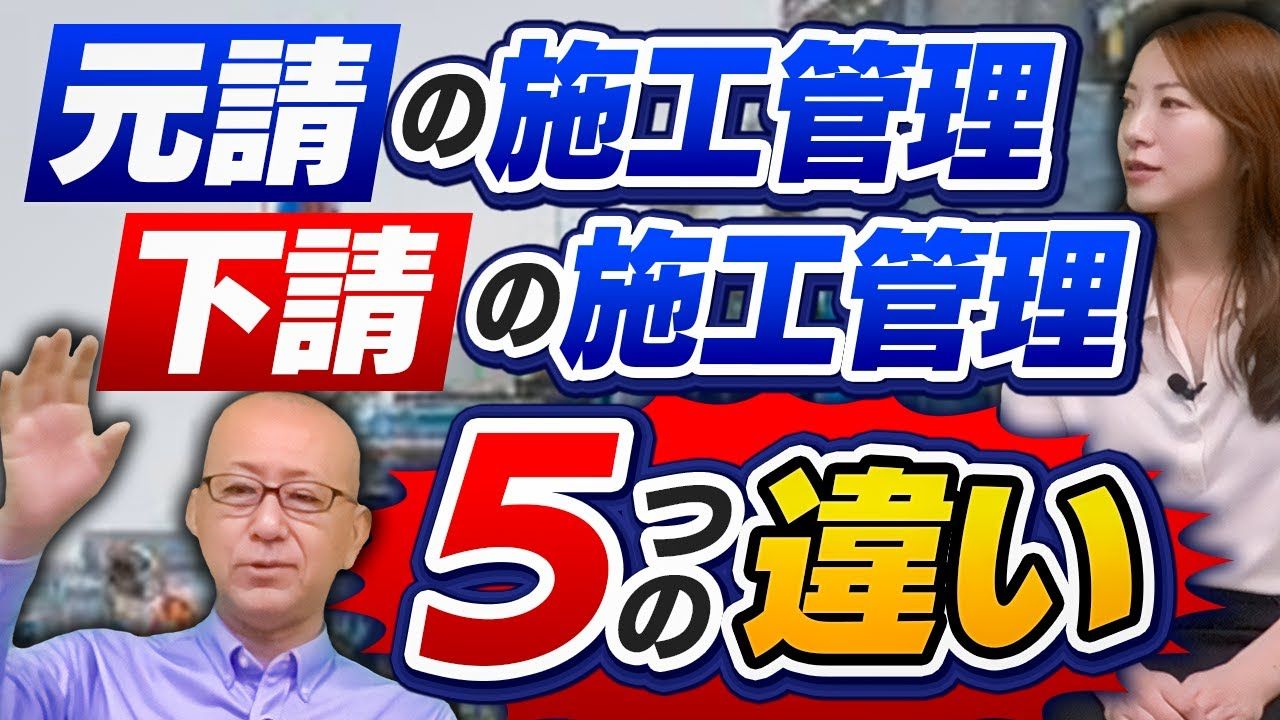下請けの表現が2026年になくなる?建設業法が改正される可能性は?
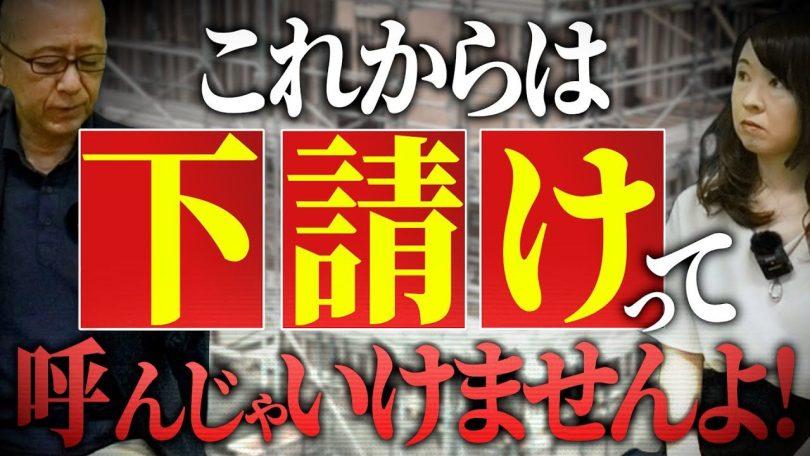
建設業界以外では、2026年から下請けの表現が使われなくなります。
2026年から下請法の改正があり、取適法に変わるからです。
参考:下請法・下請振興法改正法の概要|中小企業庁
建設業では建設業法に則るため、一見関係のない話題に見えます。
しかし建設業法からも下請けの表現が消える可能性があります。
本記事では、下請法の改正と建設業法の関係性について解説。
下請法では「下請け」のワードから連想される上下関係から、表現が変更されています。
最後までお読みいただき、建設業界の今後について考えてみましょう。
下請法の改正

建設業以外で使われている下請法が、2026年に改正されます。
正式名称は、下請代金支払遅延等防止法です。
中小零細企業や個人事業主を守るための法律。
規模が大きい企業の仕事を下請けするときに、不利な取引条件を押し付けられるのを防ぐ目的がある法律。
この下請法の改正に伴い、下請けの表現を廃止する動きがあります。
その理由は、「下請け」の表現が、元請けとの上下関係を連想させるためです。
そのため、下請法は2026年に名称を変更して改正されます。
改正後の法律名は、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律です。
略称・通称、中小受託取引適正化法や取適法といいます。
つまり下請法は2026年に改正され、法律名からも下請けの表現がなくなります。
下請けの表現がなくなった取適法
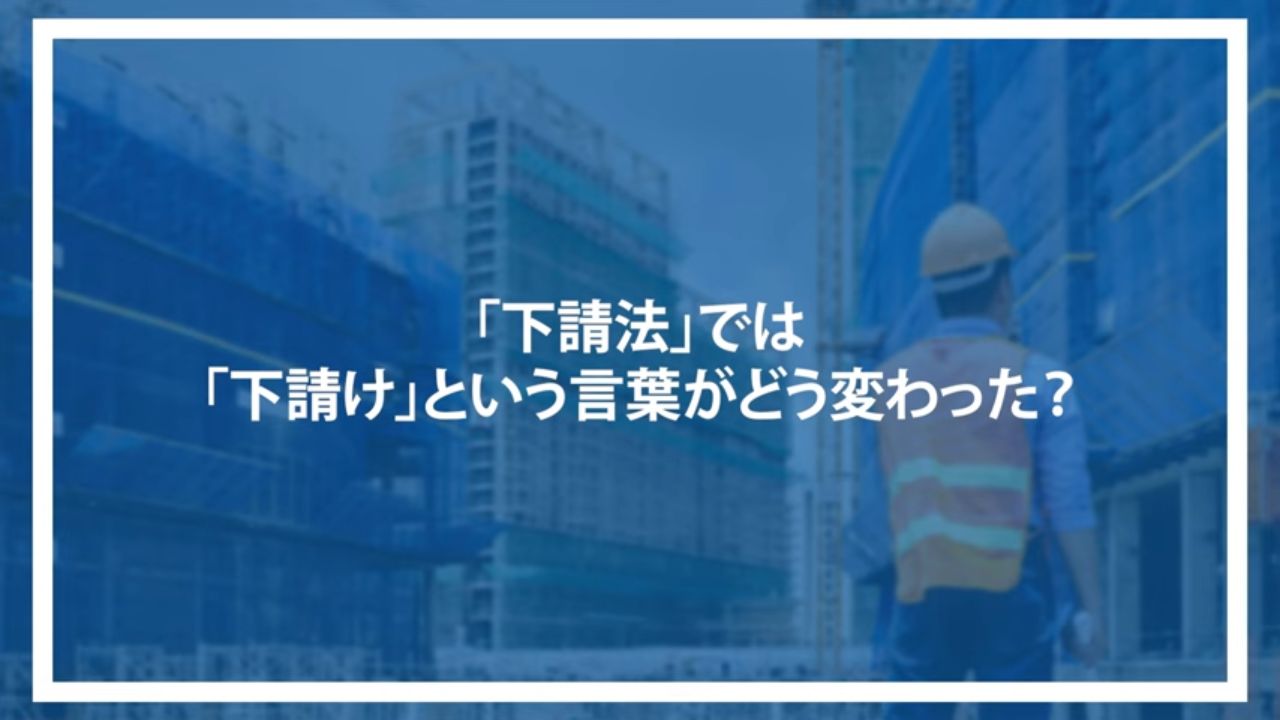
下請法で使われていた、下請事業者及び親事業者の用語は、法改正で変わります。
下請事業者は中小受託事業者に、親事業者は委託事業者に変更されます。
| 旧:下請法での用語 | 新:取適法での用語 |
|---|---|
| 下請事業者 | 中小受託事業者 |
| 親事業者 | 委託事業者 |
この用語の変更には、上下関係・主従関係のイメージを払拭する狙いがあります。
ちなみに下請法では、元請けの表現は使われていません。
親事業者の表現が使われていました。
下請法は取適法に改正されます。
さらに、下請事業者の表現は、中小受託事業者に変更です。
建設業法でも下請けの表現が消えるのか?
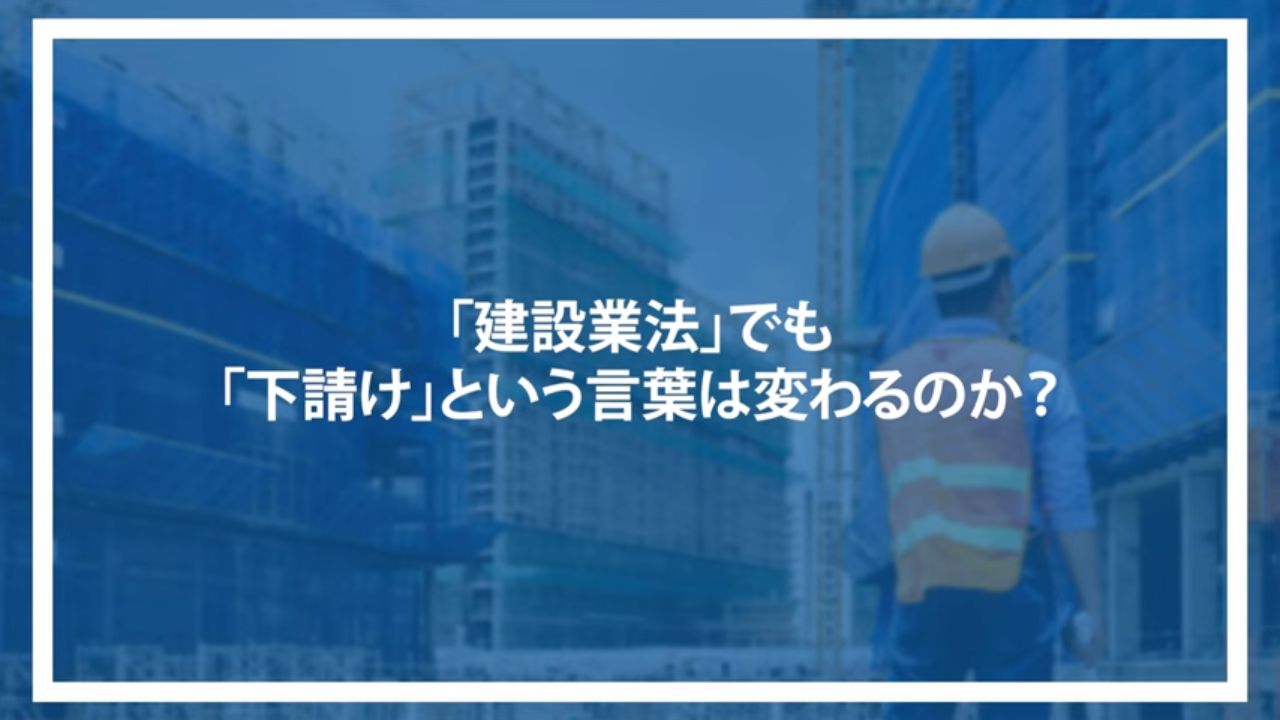
建設業界では下請法(取適法)ではなく、建設業法に則っています。
建設業法で使われる、下請負人や元請負人の用語も変わる可能性があります。
2026年からは、建設業界以外では取適法が適用され、下請けのワードは廃止です。
建設業法では、現時点で改正予定はありません。
つまり2026年以降も、下請けのワードは使われ続けます。
建設業だけ使い続けると、指摘や批判を受ける可能性は大いにあります。
「建設業法でも用語の見直しを検討すべき」という意見があるからです。
この意見に対して国土交通省の幹部は「建設業界の意見を聞いた上で検討する」と回答しています。
下請法の名称まで、取適法に変更しています。
そのため建設業界だけ下請けのワードを使い続けるのは、厳しい状況でしょう。
建設業の現場では下請けと言わなくなるのか?
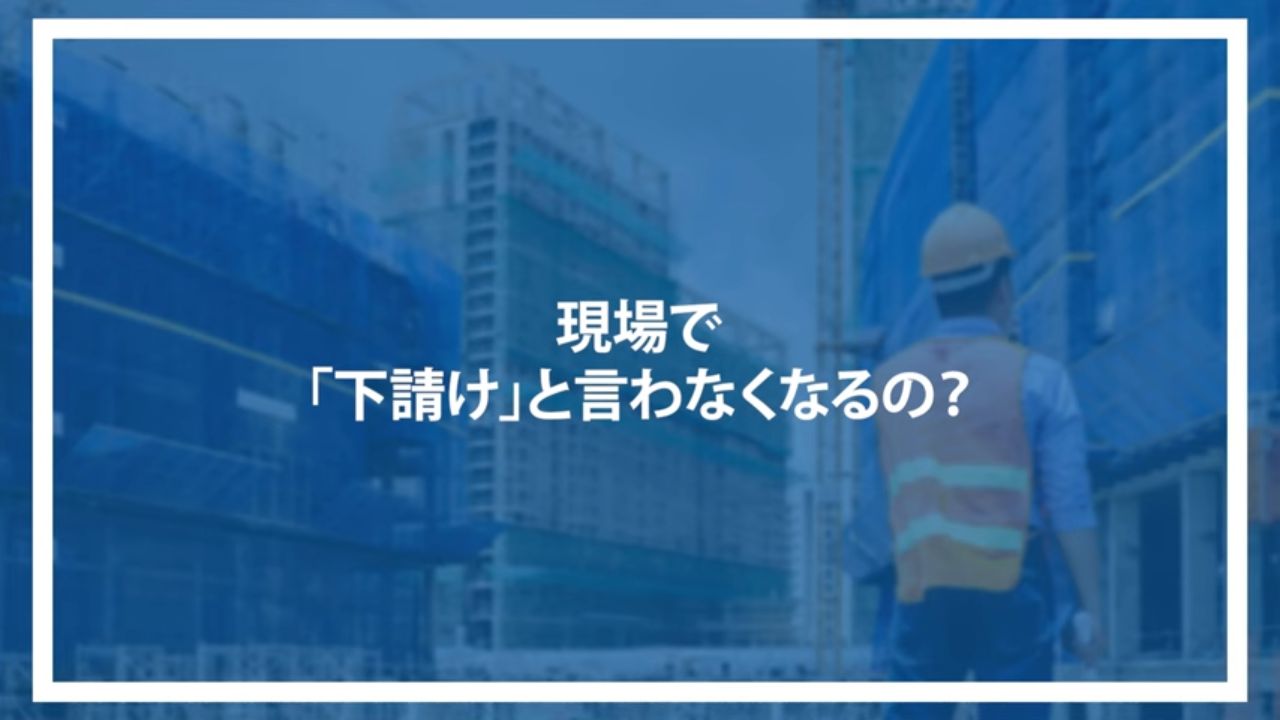
現場でも下請けと言えなくなるのでしょうか。
すでに、協力業者やパートナー企業などの呼称を用いる会社もあります。
しかし俗語として下請けが使われ続ける可能性もあるでしょう。
現在も現場では、以下の俗語が使われています。
- 1次下請:下請け
- 2次下請:孫請け
- 3次下請:ひ孫請け
建設業法で下請けの表現が変更されても、俗語として使われ続けるでしょう。
まとめ:下請けの表現は建設業法からも消える可能性は高い!
2026年の下請法改正で、建設業以外からは「下請け」の表現がなくなります。
建設業は下請法(改正後の取適法)ではなく、建設業法に則っているため対象外です。
しかし他業界に合わせて、下請けの表現を変更する可能性は大いにあるでしょう。
建設業法から下請けの表現が消えたとしても、俗語として現場で使われる可能性はあります。
今でも、孫請け・ひ孫請けのように俗語が使われているためです。
今後の建設業界の動きに着目してみましょう。
初心者でもわかる、下請けと元請け施工管理の違いは、以下の記事で解説しています。
この記事の内容は、以下の動画で解説しています。あわせてご覧ください。