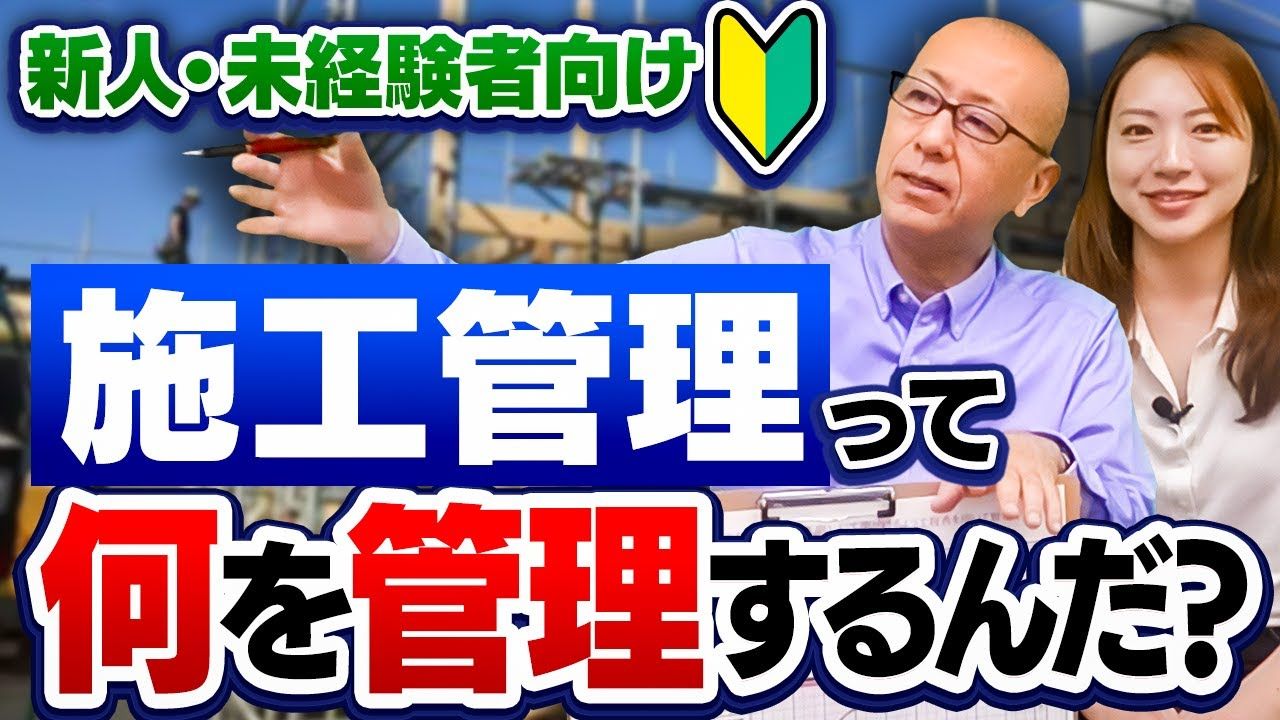社会保険って給与からいくら引かれる?2025年東京都建設業の場合の試算額
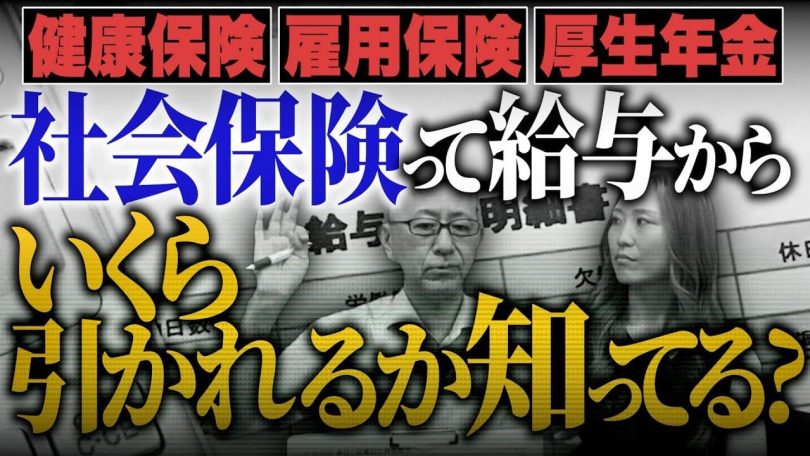
「社会保険ってなんで引かれているんだろう?」
「事務職から建設業に転職したら、天引き額が変わった気がする」
給与明細を見るたびに、毎月引かれる社会保険料の仕組みは複雑で分かりにくいと感じていませんか。さらに業界や職種が変わると、天引き額が変動するのも不思議ですよね。
社会保険料の料率は、時期(年次)、地域、職種(仕事の内容)によって細かく変わります。
例えば、事務職と建設業の現場で働く人では、労災保険の料率が異なるんです。
そこで本記事は、特に建設業界で働き始めたばかりの新人向けに、社会保険について解説しています。
社会保険の種類や、東京都の建設業で給与30万円だった場合の試算額についても紹介。
社会保険に対する「なぜ?」「なに?」が解決できますよ。
従業員と会社が日本の社会保障をどのように支えているのか、その全貌を見てみましょう。
社会保険について前提は2025年東京都の建設業

社会保険料の料率は、その時々の制度や地域、そして職種によって細かく変動します。
そこで今回の説明では、特定の前提条件を設けています。
- 時点: 2025年
- 地域: 東京都
- 業種: 建設業(建築の事業)
社会保険料率は上昇傾向にあり、2025年と2020年では料率が違います。
また、東京と千葉、沖縄、北海道、青森といった場所によっても、料率は変化。
さらに、雇用保険や労災保険のように、職種によって料率も変わります。
例えば事務職ととび職では、事故率(労災保険を使う確率)が違います。
そのため雇用保険・労災保険は、職種によって違う料率です。
本記事で用いる保険料率および試算は、以上の条件を前提としています。
社会保険の種類は6つ

一般的に、社員として加入する社会保険は「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」「子ども・子育て拠出金」「雇用保険」「労災保険」の6種類です。
これらの保険で、病気や怪我、老後生活、失業、仕事中の事故など、人生における様々なリスクに対応します。
病気やケガための保険です。病院で保険証を提示して使います。
高齢になったときの介護用保険です。対象は40歳以上。
仕事を定年した後、亡くなるまでもらえる公的年金です。
児童手当や学童保育などの制度を成り立たせるために使われるものです。これは経営者や人事を担当していないと、知らないかもしれません。
一般に失業保険と呼ばれます。仕事を失ったときに給付が受けられる保険です。
仕事中のケガに対する保険です。私的なケガは対象外とされます。
これらの保険が合わさり、広範囲にわたる社会保障制度を構成しています。
建設業の給料に対する社会保険料の割合

社会保険料の合計料率は、前提条件(2025年、東京都、建設業)に基づき給料の約3分の1(総料率32.86%)に達します。
この32.86%という総料率は、給料が30万円であれば約10万円が国に納められる計算です。
非常に大きな負担だといえるでしょう。
この費用は、会社と従業員が負担割合を決めて支払う仕組みになっています。
個別の保険料率(給料に対する割合)と負担の割合は、以下のとおりです。

会社と従業員で折半するものもあれば、会社のみ負担する社会保険もあります。
給料の約1/3が社会保険料として充当され、その費用は会社と従業員でほぼ同額を負担しています。
建設業の具体的な社会保険料の試算金額

具体的な給料の額面に対して、どの程度の金額が社会保険料として徴収されるかを知るために試算しましょう。
これは、手取り額を理解する上で非常に重要です。
前提条件(2025年、東京都、建設業)に基づいて計算した結果は、以下のとおりです。

給与30万円から引かれる従業員負担分と、会社負担分を計算すると、給与にかかる総費用が明確になります。
- 社会保険料の総額:98,580円
- 会社負担額:51,930円
- 従業員負担額(天引き):46,650円
従業員は30万円からこの46,650円が天引きされ、さらに所得税や住民税も引かれます。
会社によっては他にも、独自の天引き項目もあるでしょう。
30万円の給料に対し、国は約10万円を社会保険料として徴収。
非常に大きな金額であると、再認識させられますよね。
建設業界に社会保険に加入したがらない会社がある理由
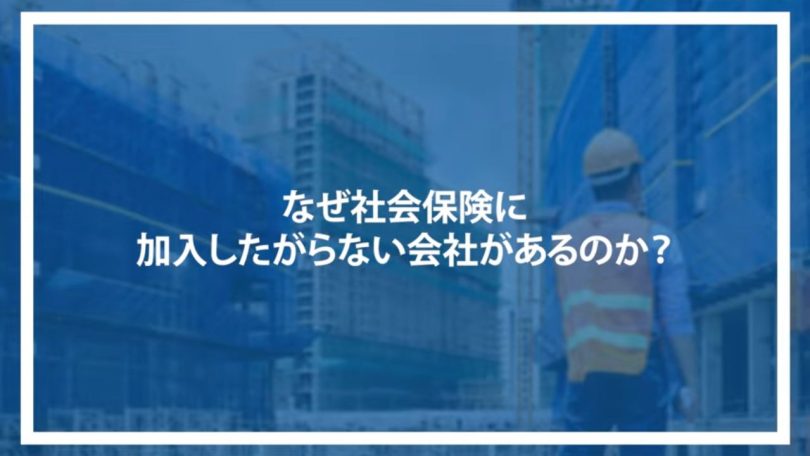
建設業界では、社会保険への加入をしたがらない会社もあります。
社会保険に加入すると、会社が負担するコストが大幅に増加するためです。
給料が30万円の従業員を雇う場合、社会保険に加入しなければ会社が負担するのは30万円。
しかし社会保険に加入すると、会社負担分の51,930円が上乗せされ、会社の実質的な総費用はおよそ35万円となります。
給料に比べて約16%〜17%の増加となり、会社にとっては大きな負担ですよね。
しかし建設業界においては、公共事業への参加には社会保険の加入が必要です。
そのため「払いたくない」ではなく、社会保険の仕組みを理解しておきましょう。
従業員を1人でも雇った場合は、会社は社会保険に加入する必要があります。
まとめ
社会保険は健康保険、年金、雇用、労災など、公的保障を提供する重要な制度です。
しかしそのコストは、給料の約3分の1に達します。
会社と従業員でほぼ折半(会社負担17.31%、従業員負担15.55%)される社会保険は、長期的な公的保障のために高い料率が必要です。
社会保険料は給与から「なんとなく引かれている」費用ではなく、日本の社会保障を支えるための必要不可欠なコストです。
これからも料率が上がるのではないかと懸念されますが、仕組みを知っておくと必要性も理解できるでしょう。
施工管理チャンネルMAGAZINEでは、初心者向けにも建設業の仕事や仕組みを解説しています。
施工管理について知りたい初心者さんには、以下の記事がおすすめです。
この記事の内容は、以下の動画で解説しています。あわせてご覧ください。