施工管理技士の第2次検定が変わる?プロ講師による出題予想&対策!
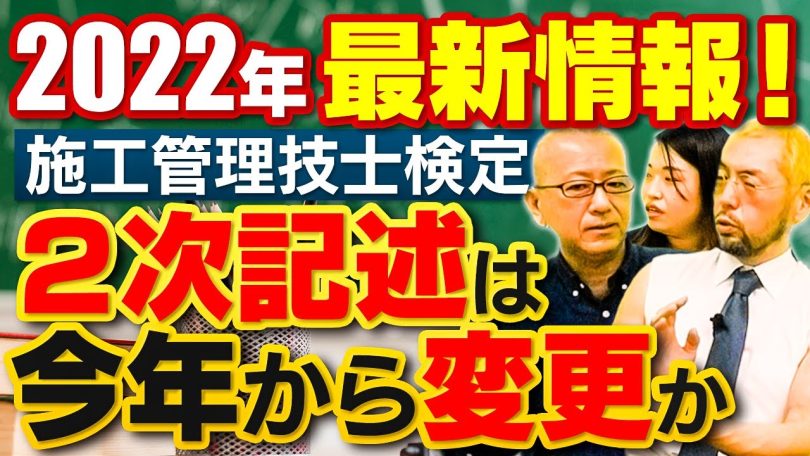
かつて施工管理技士検定では、第2次検定(実地試験)の受験で実務経験を虚偽記載した不正が発覚し、一部合格者が不合格になった事件がありました。
これを受けた国土交通省が第2次検定の”経験記述問題”を見直すと公表。
問題の内容が大きく変更されるのではと予想されています。
今回は関西建設学院にて施工管理技士検定の講師を務め、延べ1,000人余りの記述添削を行ってきたひげごろーさんに、”2次記述問題の予想と対策”について聞きました。
2021年の時点で、第2次検定問題に変更はあった?

国土交通省が問題を今後変更すると提言したのが2020年秋のことでした。
よって、早ければ2021年から変わるかもしれないと予測されていましたが、施工経験記述に関しては全く変化はありませんでした。
技士補の追加に伴った変更はあったものの、施工経験記述の出題スタイルとしては1級、2級ともに変更なしです。
たとえば土木では、工程・品質・安全に関する「現場の留意事項は何ですか?」「検討事項・実施事項は何ですか?」という出題がなされ、建築では、品質・工程・環境で「実際にしたことは何か?」などが問われました。
2022年から新問題は出てくる!?
2022年から新問題の第一弾が出題される可能性は大いにあります。
2020年に国土交通省の公表があり、2021年には新問題ができあがっていたと考えられるからです。
しかし2021年の試験に間に合わなかったのだとしたら、2022年は要注意の年と言えるでしょう。
1級・2級共に、今後受験をされる皆さんは、第2次検定変更の可能性を頭に置いておいてください。
“丸暗記ができないような問題”とは?
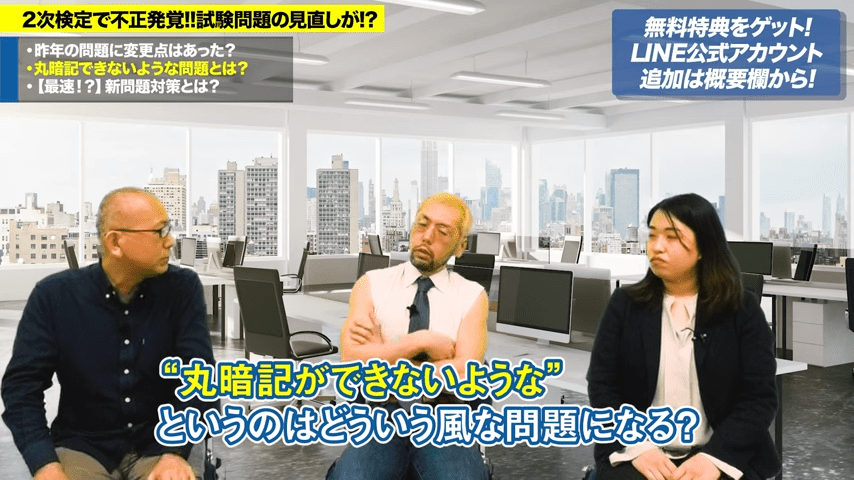
昔から施行経験記述は丸暗記が定番で、実試験では雛形に沿って自分が携わった工事規模などを当てはめると合格できるというのがスタンダードでした。
しかし、今後は丸暗記が通用しなくなるように是正が入る可能性があります。
具体的には、次のように実際に現場を知らないと回答できないような問題が問われるのではないかと考えています。
- 「実際に現場ではどのような品質管理の試験を行っていますか?」
- 「安全サイクルを用いて実際に現場ではどのようなことをしましたか?」
- 「実際に現場ではどのような施工機械を用いましたか?」
- 「どのような作業計画を作りますか?」
従来は安全・品質・工程と決まった枠組みの中で準備をすればよかったものの、今後は実際の現場風景を思い出さなくてはいけないような問題、問い方に変わるのではないかということです。
難しくはないのですが、少しひねったことを聞いてくる可能性があります。
たとえば道路であれば、出来形管理で出題された場合、「深めに掘って厚みで管理しましょう」といった回答は、現場を知っていれば事前準備がなくともすぐに思いつくはずです。
しかし現場を知らずにテンプレートしか用意していなかったら、このような問題に臨機応変に対応することは難しくなります。
つまり“丸暗記をさせない問題”とは、現場経験がきちんとあるかどうかを見定める問題のことであり、今後の第2次検定ではこのような問題が主流になるでしょう。
第2次検定、新問題の対策
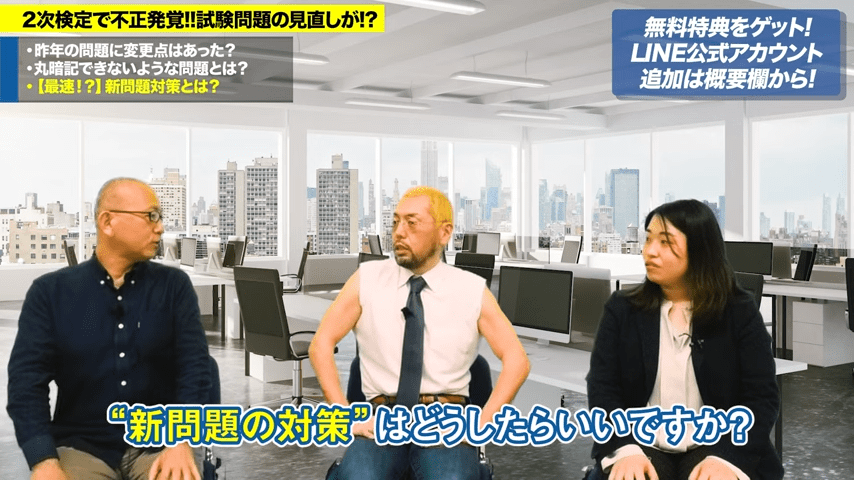
今までは丸暗記が王道の勉強法だった第2次検定ですが、新問題ではそれが通用しない可能性があります。
では具体的にどうすればいいのか、対策方法を2つ紹介します。
対策1. 項目を分散させ、具体的な現場の記述分を準備する
事前準備する文章では、特定の項目一辺倒の文章を書いてしまっている人も多いのですが、これはNGです。
そうではなく、例年聞かれている文章に「どんな重機を使うか」「請負金額はいくらか」など、具体的な内容を盛り込んでおきましょう。
たとえばコンクリートの記述をするなら、材料・養生・検査の話を盛り込むなど、1項目多めを意識して分散させた文章を準備するのです。
そうすれば実試験で特定の項目について問われた際も、その部分だけを切り取り、補足して記載するなど臨機黄変に対応できます。
特に重要なのは、何も知らない人に文章を見せて、その人が現場がイメージできるかどうかです。
書いている本人は伝わると思い込んで書いているものの、「なぜこれをしたから品質が上がるのか」「工程が円滑になるのか」と、客観的に説明できない人は意外に多いものです。
第2次検定は、1人の採点者が何十枚も採点するという点を考慮し、端的な文章を心がけましょう。
その判断に自信がない方は、ぜひ2つ目の対策も参考にしてください。
対策2. プロに添削してもらう
私が学校講師であることを抜きにしても、第2次検定については学校で学ぶことをオススメします。
最大の理由は、2次検定の記述試験は正解が発表されないため、どこが悪いのか判断のしようがないからです。
よって「何回受験してもダメなんです」という方の回答を見ると、やはり合格ラインにかすってもいないような印象があります。
このようにテンプレート自体を間違っていたり、誤解したりしていれば、どれだけ努力しても合格できないところが第2次検定の難しさです。
すでに施工管理技士に合格した先輩にチェックしてもらうのも1つの手ですが、その方の指針が合っているのかは不安が残るところ。
その点、私のように延べ1,000人以上の記述をチェックし、その合否結果も見届けてきたプロの講師なら、合格・不合格のボーダーは感覚でわかります。
特に「何回受験してもダメ」という方は、せっかくの努力を無駄にしないためにも、ぜひ学校を頼ってみてください。
意外な落し穴!?こんな人は絶対落ちます!

最後に私が授業で必ず言うことをお伝えします。
それは「綺麗汚いはともかく、字は丁寧に読みやすく書いてください」ということです。
字が汚い時点で採点されないケースは、施工管理技士検定に限らず、試験関係でよくある話です。
それから、字数を稼ぐために変なところで改行したり、変なスペースを設けたりするのもやめましょう。
あとは、トンネル・ボックスカルバート・下部工・上部工など、さまざまな工法を盛り込んだり、特殊工法を書きたがる人も多いのですが、これもNGです。
採点側が知らない工法が出てきた場合、採点者は仕様書などと見比べながら採点をします。
つまり、もし仕様書と数値が違えば減点になってしまうのです。
特殊なことを書けば書くほど採点側が採点しにくいため、私は土かコンクリート、舗装で書くことをオススメします。
まとめ
今回は施工管理技士検定のプロ講師・ひげごろーさんに、施工経験記述問題の新傾向と対策を聞きました。
より現場に踏み込んだ内容に変わることで、合格ラインにも変化がありそうですね。
今後受験される方は、この記事を参考にしっかり対策をしていきましょう!
この記事の内容は以下の動画で解説しています。
理解を深めたい方はこちらの動画もご覧ください。








