施工管理技士1級と施工管理技士2級の違いは?仕事内容・試験・年収まで徹底解説
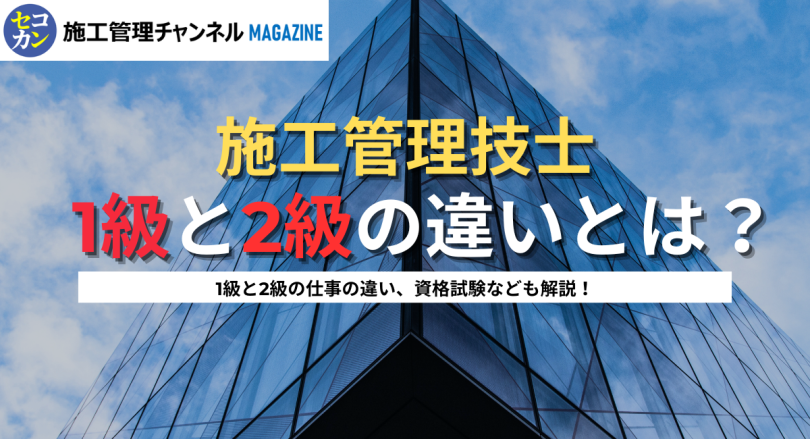
施工管理技士の資格を目指すとき、多くの人が最初に悩むのが「1級と2級の違い」です。どちらを取るべきかで、仕事内容・試験難易度・年収・キャリアの広がりが大きく変わります。
結論から言えば、
- 大規模工事や公共工事に携わりたいなら1級
- 早く資格を取り現場で経験を積みたいなら2級
が適しています。
本記事では、施工管理技士1級と2級の違いを以下の観点から徹底解説します。
- 施工管理技士の役割と資格区分
- 1級と2級の違い(仕事内容・試験・待遇・年収)
- 共通する仕事内容(四大管理)
- それぞれのメリット・デメリット
- 試験概要と合格率の比較
- キャリアアップやケース別おすすめの資格選び
この記事を読むことで、あなたのキャリアプランに合った最適な選択肢が分かり、資格取得に向けて効率的に準備できるようになります。
施工管理技士とは?
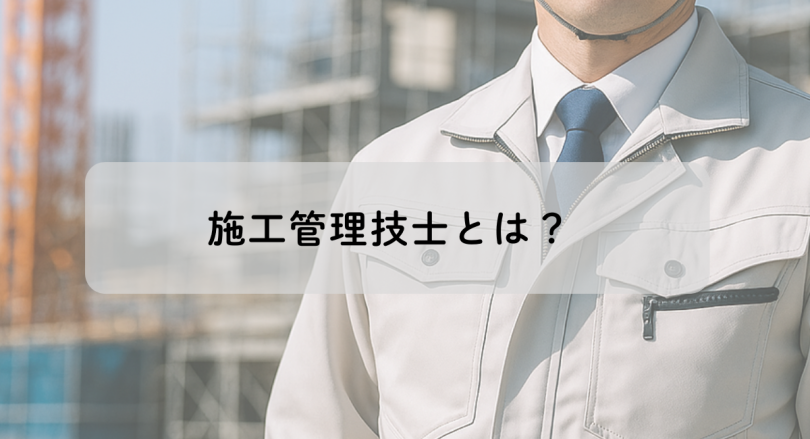
施工管理技士とは、建設現場で工事を安全に、計画通りに、そして高い品質で完成させるための国家資格を持つ専門職です。工事現場の「司令塔」ともいえる存在で、現場で働く職人や協力会社、施主との間に立ち、工事全体をまとめる役割を担います。
建設業界での役割
建設現場では「施工計画の立案」「スケジュール調整」「安全確保」「品質管理」といった管理業務が欠かせません。これを総称して四大管理と呼びます。施工管理技士は、この四大管理を実務として遂行する責任者であり、建物の完成度や現場の安全性を左右する重要な存在です。
法律上、一定規模以上の建設工事では「主任技術者」や「監理技術者」を配置することが義務付けられています。施工管理技士はその資格要件を満たすため、企業にとっても欠かせない人材です。
資格区分(建築・土木・管工事など)
施工管理技士の資格は6種類に分かれており、専門分野ごとに取得が可能です。
- 建築:住宅やビル、商業施設などの建築工事
- 土木:道路・橋・ダムなどの土木工事
- 管工事:空調・給排水・ガス設備などの配管工事
- 電気工事:送電・配電・電気設備工事
- 造園:公園・庭園などの緑地整備
- 建設機械:大型建機を使う工事の管理
このうち、最も受験者数が多く人気なのが「建築施工管理技士」です。住宅から高層ビルまで幅広く関われるため、ゼネコンやハウスメーカーで特に需要があります。
1級と2級の違い
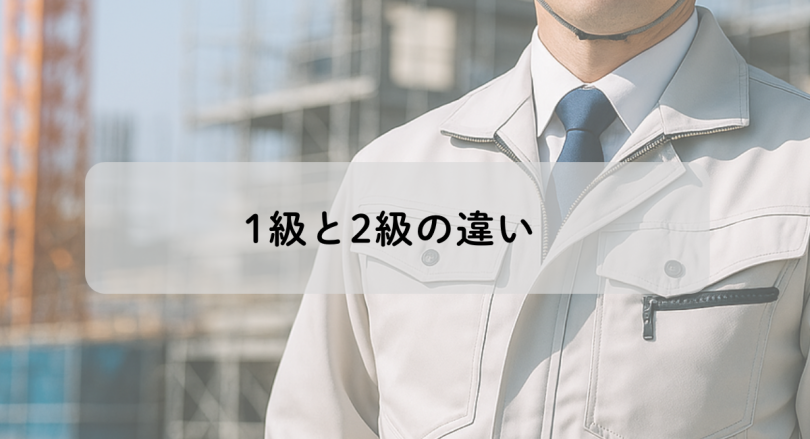
施工管理技士の1級と2級の最大の違いは、管理できる工事規模と現場での権限にあります。さらに、受験資格や試験難易度、年収・待遇の面でも差が生じるため、自分のキャリアに合わせた選択が必要です。
管理できる現場の規模と権限
- 1級施工管理技士
請負金額に制限がなく、超高層マンション・大型商業施設・公共工事など大規模プロジェクトを管理できます。監理技術者として現場に配置されることも可能で、会社の入札資格(経営事項審査)にも直結するため、企業から重宝されます。 - 2級施工管理技士
中小規模の工事を担当可能で、主任技術者として現場に配置されます。ただし、請負金額が4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)の工事は1級資格が必要です。住宅や小規模な商業施設など、地域密着型の工事が主戦場となります。
受験資格の違い
受験資格は、最終学歴と実務経験年数によって変わります。
- 1級
・大学の指定学科卒業 → 実務経験3年以上
・短大・専門卒 → 実務経験5年以上
・高卒 → 実務経験10年以上 - 2級
・大学の指定学科卒業 → 実務経験1年以上
・短大・専門卒 → 実務経験2年以上
・高卒 → 実務経験3年以上
👉 つまり、2級はキャリア初期から挑戦しやすいのに対し、1級はある程度の経験を積んでから挑戦する難関資格といえます。
試験内容・難易度の違い
- 1級試験
出題範囲が広く、学科試験では施工管理法・法規・建築学全般が網羅されます。実地試験(第二次検定)は記述式で、自身の実務経験を具体的に答える必要があり、**合格率は30〜45%**と難関です。 - 2級試験
基礎的な内容が中心で、学科はマークシート方式。第二次検定も記述ですが、専門分野(建築・躯体・仕上げ)に分かれており、比較的取り組みやすいです。**合格率は35〜45%**で、1級よりも高めです。
年収・待遇の差
- 1級
平均年収は 600万円前後。資格手当は月2〜5万円と高めに設定され、大規模案件を担当するほど昇進・昇給のチャンスが増えます。大手ゼネコンでの需要も高く、キャリアの広がりは大きいです。 - 2級
平均年収は 400万円台。資格手当は月5,000〜1万円程度で、地域工務店や住宅メーカーでの評価が中心。地元で腰を据えて働きたい人に向いています。
2級の区分(建築・躯体・仕上げ)
2級には3つの区分があり、それぞれ専門工事の範囲が異なります。
- 建築:木造住宅や小規模建築全般
- 躯体:鉄筋工事・コンクリート工事など構造部分
- 仕上げ:内装工事や仕上げ材の施工
このように1級はオールラウンドに全てを管理できるのに対し、2級は専門性を磨きながら段階的にキャリアを積む資格です。
施工管理技士の仕事内容(共通)
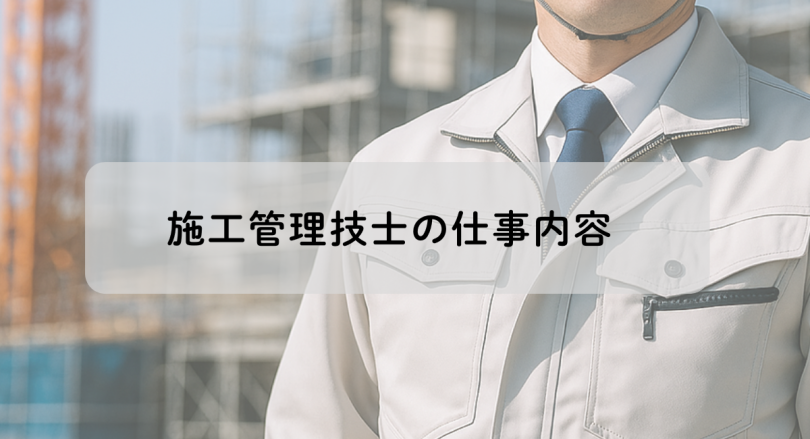
1級と2級で管理できる工事規模に違いはありますが、施工管理技士が日々行う業務内容そのものは共通しています。その中心となるのが**「施工計画」「工程管理」「安全管理」「品質管理」**の4つで、これらは「四大管理」と呼ばれます。建設現場を円滑に進めるために欠かせない役割です。
施工計画
施工計画とは、建築物を設計図どおりに効率的かつ安全に完成させるための「青写真」を描く仕事です。使用する工法や資材、必要な人員・機材、搬入経路などを細かく計画します。たとえば重機を使う工事では、安全に搬入するための手順を決めることが不可欠です。計画段階の精度が工事全体の効率やコスト、安全性を大きく左右します。
工程管理
工程管理は、工事を期日どおりに完成させるためのスケジュール調整です。複数の業者や職人が関わる現場では、作業の順序や人員の割り当てを誤ると大幅な遅延につながります。そのため、引き渡し日から逆算して計画を立て、進捗を常にチェックしながら柔軟に調整します。たとえば天候不良で外装工事が遅れた場合、別の工種を前倒しするなどの判断が必要です。
安全管理
安全管理は、現場で働く作業員や周辺住民の命を守るための最重要業務です。脚立作業での転落、火気使用による火災など、現場には多くのリスクがあります。施工管理技士は危険を予測し、朝礼で周知したり安全設備を点検したりして事故を未然に防ぎます。実際に危険行為を見つけた場合には、作業を即時中断させる判断力も求められます。
品質管理
品質管理では、建物が設計図どおりの性能や品質を満たしているかを確認します。資材のチェックや仕上がり具合の検査を行い、問題があれば是正を指示します。例えば鉄筋の配置が図面と異なる場合、放置すれば建物の強度に直結するため、早急な対応が必要です。こうした品質確保の積み重ねが、施主からの信頼にもつながります。
施工管理技士は単なる現場の監督ではなく、工期・安全・品質を守りつつ、関係者全員をまとめ上げるリーダーです。資格の等級に関わらず、これらの四大管理を遂行できることが信頼される技術者の証となります。
1級・2級それぞれのメリット・デメリット
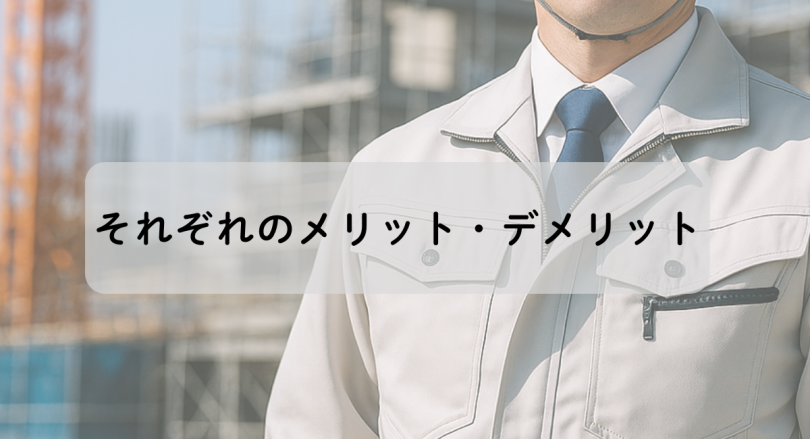
施工管理技士の1級と2級は、どちらも現場で責任ある役割を担える資格ですが、それぞれに異なる強みと制約があります。自分のキャリアプランに合わせて選ぶためには、メリット・デメリットを理解しておくことが大切です。
1級のメリット(大規模案件・年収・経営事項審査で有利)
1級施工管理技士を取得すると、大規模工事や公共工事を担当できるため、活躍の場が格段に広がります。監理技術者として配置される資格も得られ、ゼネコンなど大手企業での評価も非常に高いです。さらに、資格者は経営事項審査(経審)で加点対象となり、企業の入札に直結するため、所属先からも重宝されます。年収面でも優遇されやすく、平均年収は600万円前後と高水準です。
2級のメリット(受験しやすい・キャリアの入口)
一方、2級施工管理技士は比較的短い実務経験で受験可能な点が魅力です。学歴によっては大学卒1年で挑戦できるため、若手や未経験からキャリアをスタートさせたい人にとっては最適な入口になります。また、中小規模の住宅や商業施設など地域密着型の現場で即戦力となれるため、地元志向の働き方を望む人に向いている資格でもあります。
デメリット比較(試験難易度・費用・キャリア制限)
- 1級のデメリット
受験資格を得るまでに長い実務経験が必要で、試験も難関。学習時間や費用の負担が大きく、働きながらの取得はハードルが高いです。 - 2級のデメリット
管理できる工事規模に制限があるため、大規模案件や公共工事には携われません。キャリアの広がりという点では1級に比べて限定的で、年収面でも平均400万円台と差が出やすいです。
結論として、幅広いキャリアと高収入を目指すなら1級、早期に資格を取得して実務経験を積みたいなら2級が適しています。どちらが良い悪いではなく、自分のライフプランや働き方に合わせた選択が重要です。
試験概要と合格率

施工管理技士の資格試験は「第一次検定(学科試験)」と「第二次検定(実地試験/記述式)」の2段階で構成されています。1級と2級で出題範囲や難易度が異なり、合格率にも差があります。ここでは両者の試験内容と合格率を詳しく比較します。
1級施工管理技士の試験内容
第一次検定
施工管理法・建築学・法規を中心に出題される学科試験です。マークシート方式で、問題数は約60問。試験時間は2時間30分で、全体の60%以上の得点が必要です。施工管理法は出題数が多いため、重点的に学習する必要があります。合格すると「1級施工管理技士補」として登録可能です。
第二次検定
実務経験に基づいた応用力を問う記述式試験です。施工計画やトラブル対応など、実際の現場での経験をもとに論理的に記述する力が求められます。問題数は4問程度、試験時間は2時間30分。合格基準は60%以上で、合格すれば正式に1級施工管理技士の資格が与えられます。
2級施工管理技士の試験内容
第一次検定
基礎知識を問う学科試験で、出題は建築学・施工管理法・法規。問題数は40問、試験時間は2時間です。施工管理法の出題が多く、施工計画や安全管理に関する知識をしっかり学んでおくことが重要です。
第二次検定
選択した区分(建築・躯体・仕上げ)に応じた記述式試験です。現場経験を反映した回答が求められ、専門分野に特化した問題が出題されます。問題数は3〜4問程度、試験時間は2時間で、こちらも60%以上の得点が合格基準です。
合格率の比較
直近のデータでは以下のとおりです。
- 1級施工管理技士
・第一次検定:合格率40〜50%前後
・第二次検定:合格率30〜45%前後 - 2級施工管理技士
・第一次検定:合格率35〜50%前後
・第二次検定:合格率25〜35%前後
👉 合格率だけを見ると2級の方がやや高いですが、第二次検定の難易度はどちらも実務力が問われるため軽視できません。特に1級は記述の精度が求められるため、十分な現場経験とアウトプット練習が必須です。
結論として、1級は高難度かつ学習範囲も広いが、大きなキャリアメリットがある資格です。2級は挑戦しやすい分、早期に取得して経験を積み、ステップアップの足掛かりにするのが理想的といえます。
キャリアアップの観点
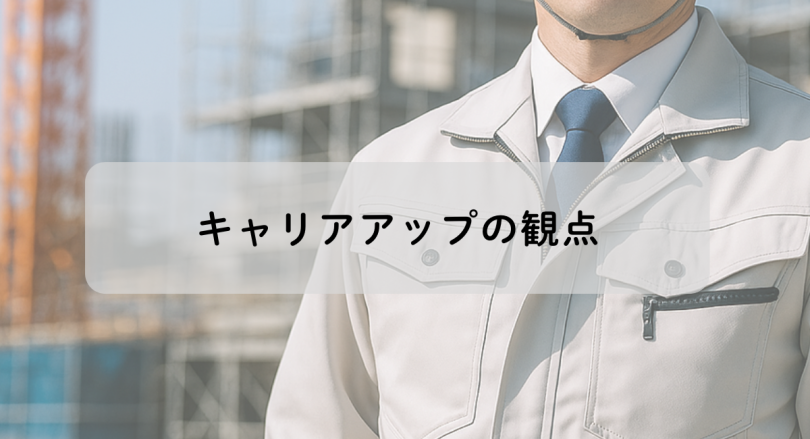
施工管理技士の資格は、単なるスキル証明にとどまらず、キャリア形成そのものに直結する武器です。特に1級と2級では、転職市場での評価や独立可能性に明確な差が出ます。
2級から1級へのステップアップ方法
まずは2級からキャリアを始め、現場経験を積んで1級に挑戦するルートが一般的です。2級は受験条件が緩やかで、若手でも早い段階で取得可能です。2級合格後に実務経験を重ねれば、1級の受験資格を得られるため、段階的にキャリアアップできる点が大きな魅力です。
転職市場での評価の違い
- 1級施工管理技士は、ゼネコンや大手建設会社から高評価を受けます。監理技術者として大規模案件を担当できるため、求人の幅も広がり、年収交渉でも優位に立てます。
- 2級施工管理技士は、地域工務店や住宅メーカーでの需要が高く、地元で腰を据えて働きたい人には強みになります。
つまり、全国規模でキャリアを広げたいなら1級、地域密着で安定志向なら2級という選択が合理的です。
独立・経営における有利さ
独立して会社を立ち上げる場合、1級資格者が在籍しているかどうかは公共工事の入札に直結します。経営事項審査での加点も大きいため、1級を持つことで経営者としての競争力が格段に高まるのです。一方、2級だけでは参入できる案件に制限があり、独立後の成長スピードにも影響します。
結論として、施工管理技士の資格はキャリアの「選択肢を増やす鍵」です。2級で基礎を固め、将来のステップアップや独立を見据えて1級を目指すのが、最も堅実なキャリア形成といえるでしょう。
どちらを目指すべき?ケース別おすすめ
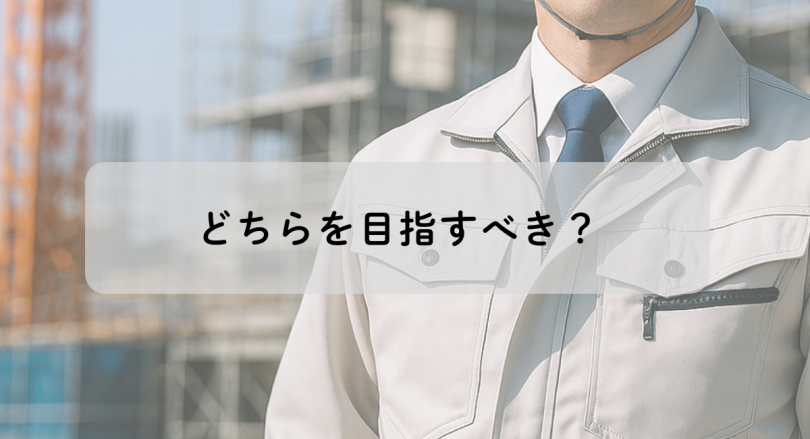
施工管理技士の資格を取得する際、最も迷いやすいのが「1級と2級、どちらを選ぶべきか」という点です。結論としては、年齢・経験・将来のキャリアプランによって適した選択肢が変わります。
新卒・若手の場合
実務経験が浅い若手は、まず2級から挑戦するのがおすすめです。受験条件が緩やかで合格もしやすいため、早期に資格を取得して現場経験を積み、将来的に1級へステップアップする流れが現実的です。
現場経験のある中堅の場合
ある程度の経験がある人は、最初から1級を目指す価値があります。大規模工事や公共工事に携わりやすく、昇進・転職市場でも高く評価されます。すでに施工管理の基礎を理解している中堅層にとって、1級はキャリアアップの決定打になります。
将来独立・管理職を目指す場合
独立して会社を経営したい、あるいは企業内で管理職を目指したいなら、1級は必須資格です。公共工事の入札条件にも直結し、経営事項審査で有利になるため、企業にとっても欠かせない人材として評価されます。
まとめると、キャリア初期は2級、中堅以上や独立志向なら1級が最適な選択です。将来のキャリア像をイメージしながら、自分に合った資格を選びましょう。
施工管理の最新情報を知るなら「施工管理チャンネルMAGAZINE」へ

施工管理技士の資格やキャリアを考える上で、最新の業界動向や試験制度の改正情報を把握することは欠かせません。特に施工管理技士の試験は受験資格や出題傾向が見直されることも多いため、常に新しい情報をキャッチアップしておくことが重要です。
そこでおすすめなのが、公式メディア「施工管理チャンネルMAGAZINE」です。資格試験の最新情報、転職・キャリア形成のコツ、現場のリアルな声など、施工管理技士を目指す方や現役で活躍する方に役立つ情報を幅広く発信しています。
まとめ
施工管理技士1級と2級は、仕事内容自体に大きな差はありませんが、管理できる現場規模・試験難易度・年収・キャリアの広がりにおいて明確な違いがあります。
キャリア初期の方は受験しやすい2級から挑戦し、経験を積んで1級へステップアップするのが現実的です。一方で、将来的に大規模工事や独立を目指すなら、1級取得が必須といえるでしょう。
大切なのは「今の自分に必要な資格はどちらか」を見極めることです。違いを理解したうえで、自分のキャリアプランに最適な選択をしていきましょう。








