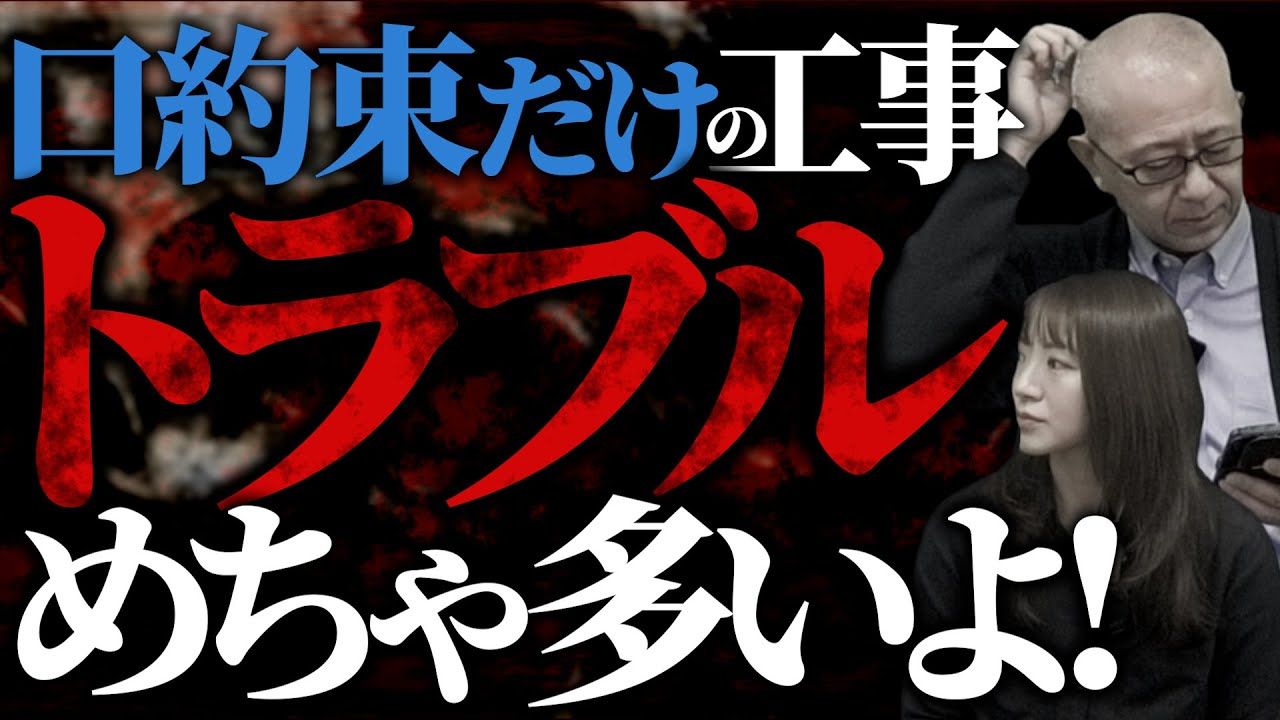下請から選ばれるゼネコンへ|元請が絶対的な時代は人手不足により終わった
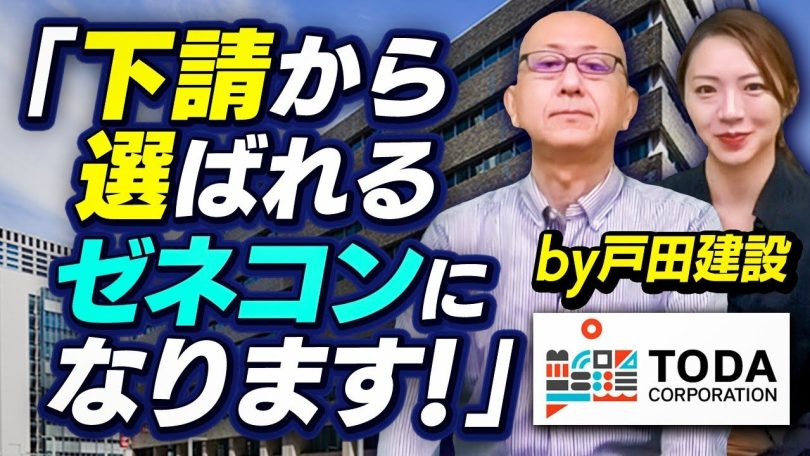
「下請から選ばれるゼネコン」
戸田建設がこのようなゼネコンを目指しているのをご存知ですか。
戸田建設は協力会社や取引業者の約5,000社に対して、満足度調査を実施。
選ばれるゼネコンになるために、満足度向上を目指しています。
本記事では、戸田建設の満足度調査について解説しています。
調査から得られたのは、やはりコストの課題でした。
この調査から、建設業界の構造が大きく変わりつつある、と分かります。
建設業界の今が知れる、施工管理チャンネル by 株式会社ライズ。
最後までお読みいただき、流れの変化を知ってください。
下請・協力会社から選ばれるゼネコンを目指す戸田建設

戸田建設が取引先の満足度を調査したニュースが、日刊建設工業新聞2024年1月12日の紙面に掲載されていました。
取引先満足度調査の目的は、施工体制の維持・強化です。
協力会社組織である利友会(りゆうかい)や取引業者など、約5,000社からの満足度を調査しました。
調査結果より得られた課題から、対応策を具体化。
「協力会社から選ばれるゼネコン」を目指すとしています。
大谷社長は「ステークホルダーの満足度を高めることが企業価値向上につながる」とコメントしています。
※ステークホルダー:利害関係者つまりは取引先のこと
ちなみに戸田建設は、このような取り組みを以前から実施しています。
- 2021年度:従業員満足度調査
- 2022年度:顧客満足度調査
- 2023年度:取引先満足度調査
取り組みを通して、従業員や顧客に対する解決策を講じてきました。
手持ちの工事・案件を順調に消化するには、職人や現場監督の確保が必須です。
ゼネコンにとって職人は下請工事会社。
職人不足が叫ばれる中、下請工事会社の意見を聞き改善しなければならないと、危機感を持っています。
そのため戸田建設は2023年度に、取引先からの満足度向上を目指す調査を実施しました。
職人の人手不足については、以下で詳しく解説しています。
下請・協力会社や取引先への満足度調査内容
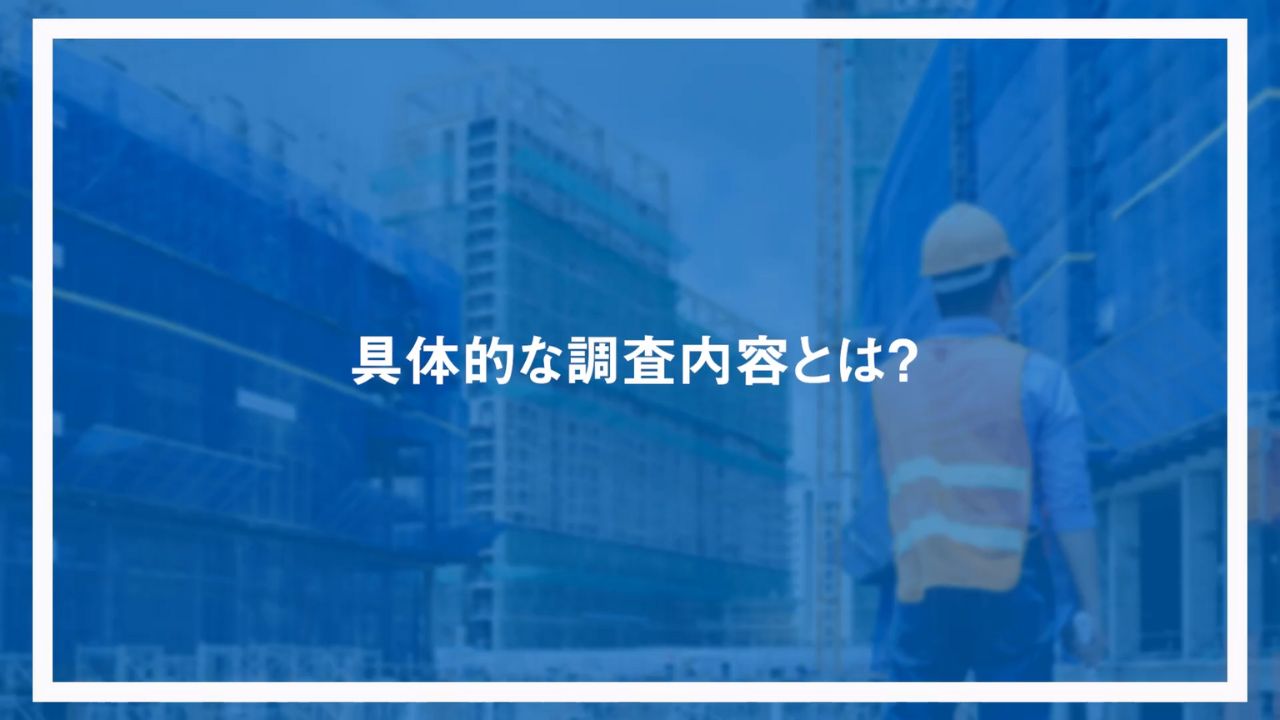
戸田建設は取引先の満足度向上を目指して、具体的に以下の内容で調査しました。
調査対象は、およそ5,000社です。
| 項目名 | 社数 |
|---|---|
| 利友会 | 1,415社 |
| 過去3年間の取引会社 | 3,537社 |
| 合計 | 4,952社 |
戸田建設の取引会社の会。
調査したのは、納得できるコストか、適切な工期かだけではありません。
安全や士気(モラル)、環境、ロイヤルティーなどの30項目に、5段階評価してもらいました。
結果として、コストの問題を中心に、ギャップや課題が得られたそうです。
下請・協力会社が仕事を選ぶ時代

調査結果に対して、戸田建設の大谷社長は以下のようにコメントしています。
一方的に意見を聞き、発注金額を上げる。これでは競争力がなくなってしまう。
様々な工夫を凝らして、協力会社の期待に応じる姿勢を見せたい。
「戸田建設の現場で働きたい」と言ってくれる取引先・協力会社が集まるように、力を高めたい。
建設業、とくに技能職・職人は人手不足です。
高齢化と後継者不足により、廃業する会社もあります。
業界の流れは昔と変わり、下請会社が仕事を選ぶ時代です。
元請が「アレやれ」「コレやれ」という時代は終わりました。
元請と下請のパワーバランスが変わった
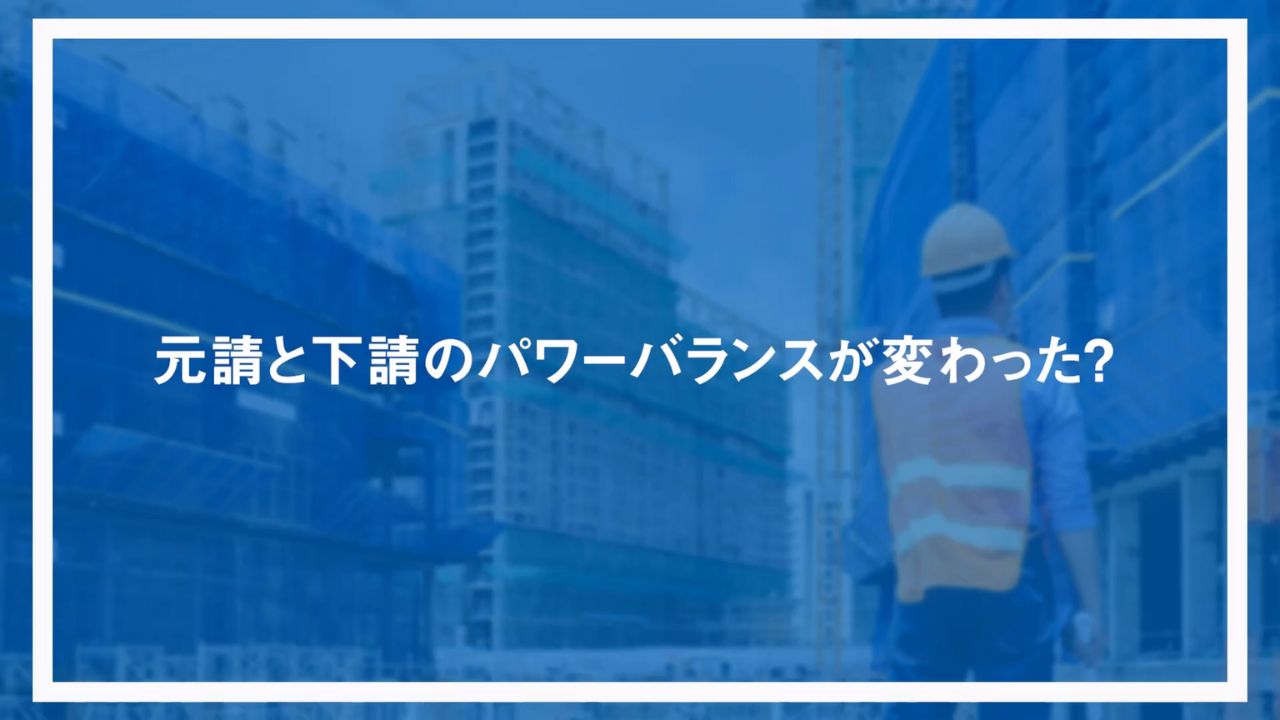
元請が「下請・協力会社から選ばれるゼネコンを目指す」のは、一昔前と比べると隔世の感があります。
すべてのゼネコンが、戸田建設のように下請会社から選ばれようとしているわけではありません。
しかし大手ゼネコンが、このような目標を持つこと自体、信じられない状況です。
スーパーゼネコンや大手ゼネコンの下請に入るには、協力会に入会する必要がありました。
さらに入会するには権利があり、どこの会社でも下請になれたわけではありません。
会員権売買があり、1,000万円ほど必要としていた協力会もありました。
ゼネコンには絶対的権力があったのが、一昔前です。
さらに口頭で依頼・施工し支払いが滞る(最悪の場合支払われない)ケースもありました。
※口頭契約はトラブルもあるため注意
このような時代から考えると、隔世の感がありますよね。
ゼネコン側が「取引してください」とお願いしている状況です。
元請が絶対的権力を持った時代は終わり、下請にお願いする側へ変わりつつあるといえるでしょう。
まとめ:下請に選ばれるよう元請がお願いする時代になった
戸田建設の調査では、おもにコスト面での課題が得られました。
一昔前であれば、元請が絶対的権力を持っていた時代。
しかし職人不足となった今では、下請が仕事を選ぶ時代になりました。
それでもXのようなSNSには、下請けイジメの悩み・不満もお見受けします。
人手不足だからこそ、元請と下請がお互いを思いやって仕事を進められる形が一番ではないでしょうか。
この記事の内容は、以下の動画で解説しています。あわせてご覧ください。